第六話 牙城クスコ(10)
さて、その頃、抜け道を進んできたトゥパク・アマルとロレンソは、いよいよクスコの市街地に近づきつつあった。
さすがにクスコ出身のロレンソはこの界隈の地理に明るく、獣道や裏道を巧みに経由して、クスコの城門を通らずに見事に役人たちの目をかすめ、目的地――褐色の敵将フィゲロアの屋敷――に迫りつつあった。
月明かりも無い曇天の夜空は、二人をうまい具合に夜闇に包み、その身を隠すのに一役買ってくれた。
山岳地帯の草地を抜け、いよいよクスコの市街地に迫り、草の陰から様子をうかがう。
この界隈まで来ると、人通りも徐々に増してくる。
時刻は、まだ、夜九時を回ったばかり。
さすがにクスコ市の中心部に近いこの辺りは、役所や数々の商店、比較的身分の高い者たちの立派な屋敷などが林立しており、夜でも華やいだ雰囲気に包まれている。
その気配は、スペイン的気風の強い首府リマとはまた異なり、やはり随所に残るインカ時代からの精緻な石組みや建造物のためだろうか、かつてインカの都であった頃の名残を確実に留めており、トゥパク・アマルの深い郷愁を誘った。
暫し、その雰囲気に目を細めて感じ入った後、トゥパク・アマルは頭から被ったベールの陰から、その切れ長の目だけを動かしてロレンソを見た。
恐ろしく美しい女性から流し目を受けたような錯覚を覚えて、相手がトゥパク・アマルだと頭では理解していながらも、ロレンソは一瞬ドキリとしてしまう。
「ロレンソ殿、そなたの導き、誠に的確なものであった。礼を述べるぞ」と、トゥパク・アマルはその瞳で静かに微笑み、さらに、声を低めて続ける。
「ここからは、わたし一人で参る。
そなたは、この辺りの草地に身を隠し、待っていておくれ。
帰り道も、また案内を頼みたい」
「え?!
まさか…トゥパク・アマル様、お一人で行かれるのですか?!」
思わず驚愕してロレンソが声を上げる。
「シッ…――」と、トゥパク・アマルはロレンソに目配せすると、再び、いつものように、案ずるな、と瞳で微笑む。
「二人で行っては、かえって目立ってしまう。
大丈夫だ」
そして、周囲を鋭い目でざっと見渡してから、人通りの切れたタイミングを見計らって、素早い身のこなしで草地から道へと出た。
(トゥパク・アマル様…――!!)
草地に身を潜めたまま、非常な心配を滲ませた目で喰い入るように見据えているロレンソに、トゥパク・アマルはもう一度、案ずるな、とその瞳で深く頷くと、すっと前方に視線を向け、そのまま市街地の雑踏の中に紛れていった。
 女性に扮したその姿で、顔を隠すようにうつむき加減になりながらランプの灯りの下を往くトゥパク・アマルの姿は、いかに夜闇に紛れようとしても、やはり、その優雅で美しい雰囲気や身のこなし、そして理屈を超えて漂うどうしようもない存在感が、いかようにも人目を惹きつけずにはおられなかった。
女性に扮したその姿で、顔を隠すようにうつむき加減になりながらランプの灯りの下を往くトゥパク・アマルの姿は、いかに夜闇に紛れようとしても、やはり、その優雅で美しい雰囲気や身のこなし、そして理屈を超えて漂うどうしようもない存在感が、いかようにも人目を惹きつけずにはおられなかった。
路往く人々は、スペイン人、インカ族を問わず、また老若男女を問わず、皆、そちらを振り向き、また、連れ立っている者たちは感嘆を漏らし合い、あるいは、何やら耳打ちし合いながら視線を投げてくる。
トゥパク・アマルは彼らの目を避けるように、いっそう、うつむき加減を強め、その歩みを速めた。
もちろん、常に周囲に鋭く警戒のアンテナを張りめぐらせながら。
インカ帝国の旧都であるこのクスコには、これまでの人生の中で、もう幾度にも渡って来訪しているトゥパク・アマルにとって、斥候によって報告された敵将フィゲロアの屋敷の場所を見つけることなど何の難儀もなかった。
もちろん、フィゲロアは本来は首府リマに拠点をもつため、このクスコの屋敷は今回の討伐隊に加わっている間の仮住まいであろうけれども。
かくして、ほどなく、トゥパク・アマルはその屋敷の前に姿を現した。
門前には、厳(いかめ)しい風貌の兵たちが、鋭い眼光を利かせながら警護に当たっており、さすがに戦時下らしいものものしい雰囲気である。
それら衛兵たちがインカ族の者たちであることに、彼は改めて皮相な感情を抱きつつ、静かな足取りで門前に向かう。
インカ族の衛兵たちが、女装のトゥパク・アマルを素早く取り囲んだ。
「おまえ、何者だ。
何用か?!」
厳しく訊問してくる兵たちに、トゥパク・アマルは無言で頭を下げた。
衛兵たちが不審そうに目配せする。
トゥパク・アマルはうつむき加減になったまま、ベールの隙間から美しい切れ長の目だけを覗かせ、その目元を細めて妖艶な微笑みを送る。
それから、優美な仕草でスッと己の指先を出すと、中心にいる一人の衛兵の手を取った。
思いもかけぬ夜間の「美女」の来訪に内心驚き、密かに心浮き立たせている衛兵たちは、その手を取られて警戒よりも、むしろ嬉しそうでさえある。
トゥパク・アマルは、僧衣の袖飾りの中にその手の全容を殆ど隠したまま、しかし、指先だけを微かに覗かせて衛兵の手を取っている。
そして、その衛兵の手の平に、滑らすようにしながら、もう一方の手の指先を慎重に乗せた。
実際、トゥパク・アマルの、そのしなやかな指先だけを見れば、十分に女性の手に見えた。
トゥパク・アマルは、じらすように一呼吸おくと、『わ・た・し・は』と、何やら文字を綴りはじめる。
もちろん、インカの公用語であるケチュア語には文字がないので、彼が綴る文字はスペイン語である。
「どうやら、この女、言葉を喋れないらしい」と目配せし合う兵たちは、しかしながら、すっかり眼前の麗しいその女性――に扮したトゥパク・アマル――に目を奪われ、気もそぞろの様子であった。
トゥパク・アマルは少々身を屈め、あえて上目遣いになりながら、その目元にいかにも美しい微笑みを浮かべて、衛兵の手の上に、さらに文字を綴っていく。
『フィゲロア・さ・ま・の・母上・の・使者・と・し・て・参・り・ま・し・た。・火急・の・用・な・れ・ば・直接・お・目・に・か・か・り・た・い・の・で・す』
役人たちは再び目配せし、それから、トゥパク・アマルを警戒の混じった目で見る。
憂いを秘めた、いかにも美しく、しかも相変わらず妖艶でさえある微笑みを流し送ってくるトゥパク・アマルを、衛兵たちはもはや直視できない様子で、そのうちの一人の兵が上擦った声で「フィゲロア様にお伺いして参る」と、屋敷の中に消えた。
しかし、母上様からの火急の使者が、しかも、女性が一人でやって参りました、と聞かされたフィゲロアが、もちろん強い疑念を抱かぬはずはなかった。
「怪しき者、通さずに門前に留めよ!」と言い残し、フィゲロアは門の方を見渡せる屋敷の二階へと向かった。

(そう、あの者が、疑いをもたぬはずはない…)
そう思いながらトゥパク・アマルも、また、門前から屋敷の窓の方を見上げた。
案の定、かの褐色の敵将フィゲロアが、屋敷の二階の窓辺にその姿を現した。
そして、非常に鋭い目でこちらを見下ろす。
トゥパク・アマルも、その場から、真っ直ぐにその窓を見上げた。
そして、すっと、その目を細める。
フィゲロアの眼の中に、さすがに驚愕の色が浮かぶ。
(まさか…――!!
いや、しかし、あれは…!!)
あの切れ長の目、あの背丈、あの髪、あの雰囲気…には、明らかに見覚えがあった。
戦場で命を懸けて対峙した相手のことは、動物的な勘が、己の体の底に覚えさせている。
いかに姿を変えてこようとも、そのような表面的なものなど、血肉に刻み込まれた記憶と直観が、あまりにも容易(たやす)く剥ぎ取ってしまう。
フィゲロアは、改めて、目を凝らした。
トゥパク・アマル?!間違いない!!
一人で来たのか?まさか…――!!
一方、門前では、既に相手に正体が知れたであろうことを悟っているトゥパク・アマルが、褐色の敵将に向かって、その眼差しで深く礼を払う。
それから、両手を広げ、武器など持ってはいない、と、窓辺に向かって合図を送る。
そして、フィゲロアの瞳を貫くように見据え、その目で力強く訴えかけた。
(そなたの話を聞こう。
わたしの話も聞いてくれ。
話し合おう!!)
フィゲロアの目に、あの戦場で見せたのと同様の憎悪の炎が燃え上がる。
しかし、トゥパク・アマルは、じっとその目を見つめ返した。
この後の、インカの民の命運はこの瞬間にかかっている…――!!
トゥパク・アマルの瞳の中にも蒼い炎が激しく燃え上がった。
それと同時に、彼の全身から、あの青白い光のようなものが強く放たれはじめる。
その光はトゥパク・アマルの全身を包み渦巻くようにしながら、天空に立ち昇っていくようにさえ見える。
フィゲロアは、言語を絶する苦々しい思いを噛み締めながらも、しかしながら、突如、眼下に現われ出(い)でたそのトゥパク・アマルの纏う覇光に、どうしようもなく心を揺さぶられる激しい感覚に突き動かされずにはいられなかった。
窓辺に添えた彼の褐色の逞しい指に、いつしかひどく力がこもっている。
フィゲロアは唇を強く噛み締めた。
(話し合いなど、無駄なこと…――!
トゥパク・アマル…おまえとは、あまりにも向いている方向が違うのだ!!)
フィゲロアは、己の内側に湧き起こる様々な想念を振り払うように、眼下のトゥパク・アマルを鬼のような形相で激しく睨みつけた。
だが、そのようなフィゲロアの様子になど微塵も臆することなく、トゥパク・アマルは厳然たる眼差しで、こちらを真っ直ぐに見上げている。
厳かな僧衣を身に纏い、青白い光に包まれていく神々しいようなトゥパク・アマルの姿は、さすがのフィゲロアの目にも、まるであの世からの使者の光臨のようにさえ見えてくる。
フィゲロアは、己がとらわれた錯覚を懸命に振り払うようにして、目をこすった。
気を落ち着けてから、再び、眼下を見下ろす。
だが、やはりそこには、先ほどよりもいっそう強烈な強いオーラのような光を放ちながら、清冽な蒼い炎を燃え立たせた眼差しで、まるで地上に降り立った大天使のごとくに悠然とそこに現われ出(い)でているトゥパク・アマルの姿が見える。

その煌々と光輝くような強烈な存在感の源流を為しているものは、インカ皇帝の正当なる末裔としての、ゆるぎなき自覚と自信の表れなのか、あるいは、その比類なき重責を担う命運の甘受…――そのことの表れなのか。
今、フィゲロアは己の心に燃え盛る、トゥパク・アマルに対する黒々とした殺意に彩られた敵対心を明確に自覚しながらも、しかし、何としたことか、同時に、己の中で、トゥパク・アマルに対する理屈を超えた異様に引き込まれるもの…それは、まるでこの瞬間に何かの魔術にかけられたかのような、激烈な引力のごとくのものを感ぜずにはいられなかった。
かくして――…結局、彼は衛兵を呼び戻し、トゥパク・アマルを己の屋敷に通させたのだった。
果たして、トゥパク・アマルと褐色の敵将フィゲロアとは、屋敷の一室で、格調高い調度の施されたテーブルを挟み、ついに1対1で対峙するに至った。
フィゲロアの眼前で、トゥパク・アマルは落ち着いた手つきで、己の顔を覆っていた布を取り去っていく。
美しくも、非常に精悍な本来のトゥパク・アマルの相貌を目前にして、フィゲロアは改めて息を呑んだ。
トゥパク・アマルも、今、やっと直近で向き合うことのできた褐色の敵将に、熱い視線を向けながら、その目を細める。
フィゲロアは、漆黒の巻き毛に縁取られた生気溢れる凛々しい風貌に、あの目を見張るような真っ直ぐで純粋な眼差しを備え、その透明な深海のごとくに澄み切った黒い瞳の色は、こうして傍近くで見るといっそう際立った輝きを放っている。
しかしながら、トゥパク・アマルの目の中で、その褐色の敵将の純真無垢な瞳の中に、あの激しい憎悪の焔が再びメラメラと燃え上がりはじめた。
トゥパク・アマルも、今、この瞬間にインカの命運を賭けるがごとくの気迫をその目元に湛え、その瞳にはあの蒼い炎がまた燃え立ちはじめる。
互いの中に燃え上がる炎を射抜くがごとくに、二人の目がいっそう鋭い光を放ちながら真正面から貫き合った。
そうしながらも、トゥパク・アマルは、「フィゲロア殿、そなたとこうして話す機会を与えてくれたことに、深く感謝いたす」と真摯な声で語り、己の頭を下げて丁寧に礼を払った。
奇しくも『インカ皇帝』に頭を下げられた形となり、さすがのフィゲロアも、瞬間、その瞳にやや臆した色を浮かべる。
が、急いで、それを払拭するように、再び険しい眼差しをつくった。
トゥパク・アマルは真正面から、単刀直入に問いかける。
「そなた、何故、インカ族でありながら、スペイン側につこうと考えたのだ?」
問いかけるその声は、決して非難がましいものではなかった。
互いにとって納得しがたい行為であったとしても、それぞれが真剣に考えて出した結論であり、選択した行動なのだ。
トゥパク・アマルは深く誠意を込めた目で、改めて敵将を見つめる。
「そなたなりの考えがあってのことであろう。
聞かせてほしい」
「おまえこそ…」と、フィゲロアはトゥパク・アマルに向かって言いかけ、しかし、恐らく、「おまえ」などと、そのような粗野な呼び方を眼前の人物にすることに、彼の無意識は強い抵抗を覚えたのであろう。
そのイントネーションは、どうにも不自然な、違和感を帯びたものであった。
フィゲロアは、思わず、言葉を選びあぐねたように口ごもる。
そして、その僅かな沈黙は、この褐色の敵将が、本来は他者を深く尊重する、礼儀正しき人物であることを十分に暗示していた。
トゥパク・アマルは穏やかな眼差しで目を細め、「構わぬ。そのまま続けよ」と、フィゲロアの言葉の続きを促す。
当のフィゲロアは仕切り直すように咳払いをすると、鋭い声で言った。
「おまえこそ、何故、このような反乱行為なぞ起こしたのだ。
おまえの、真意は何だ?
己の為してきたことを、頭を冷やして振り返ってみよ…!
多くの殺戮と、キリスト教の破壊!!
悉く秩序を乱し、今や民の犠牲は計り知れず…!
あの何万という屍の山をつくりだしたのは…誰なのだ?!
答えてみよ…トゥパク・アマル!!」
語り続けるうちに次第に苛立ちを強め、やがて挑みかかるように乗り出しはじめたフィゲロアに、トゥパク・アマルは、その思いを受け留め、包み込むような眼差しを注ぐ。
それは、まるで保護者のごとくの落ち着き払った表情であり、態度であった。
だが、そんなトゥパク・アマルの様子に、いっそういきり立ちながらフィゲロアが続ける。
「トゥパク・アマル…表向きは、何とでも言えよう!
だが、おまえの真意は何だ?!
これほどまでの犠牲を出して、おまえは…一体、何が望みなのだ?!」
憎々しげに言い放つフィゲロアに、トゥパク・アマルは沈着な声で言う。
「この反乱の目的は、このインカの地に生きる全て民の復権。
つまりは、インカ族、混血児、当地生まれの白人、黒人たちが、スペイン渡来の白人たちと等しく権利を有する、そして、それが実際に行われる治世を築くためだ」
フィゲロアの視界の中で、そう語るトゥパク・アマルの周囲に、青白く光るものが再び漂いはじめるのが見える。
その錯覚をいなすようにしてフィゲロアは軽く頭を振り、それから、険しい表情を返した。
そして、「それだけか?」と、疑いに満ち満ちた視線を向けて、その目を訝しげに細めた。
「『インカ皇帝』として返り咲き、再び、この地の絶対的主権者として君臨したいのではないのか?!」
激しく皮相な色を帯びた目で、その中にさらなる憎悪の炎を燃え滾(たぎ)らせながらフィゲロアが憎々しげに言う。
トゥパク・アマルは体ごと真正面からフィゲロアを見据えた。
それから、微かに目を細め、噛み締め、諭すように言う。
「それは違う。
もはや、時代は移った。
わたしは、皇帝の座につくことなぞ考えてはいない」
フィゲロアは、相変わらず疑いに満ちた、不審の眼差しを変えない。
「口先では、何とでも言えよう」
トゥパク・アマルは暫し無言で、その純白の袖飾りから覗いた褐色のしなやかな指をテーブルの上で静かに組んだ。
そして、思慮深い眼差しになってその指に視線を落とし、それから、再び、ゆっくりとフィゲロアの方に視線を戻した。
全く偽りの感じられない、非常に澄んだ真摯な眼差しである。
トゥパク・アマルのその目の色は、本質的にはとても純粋なフィゲロアの心に、理屈を超えて、真っ直ぐに訴えかける力を十分に有する種類のものだった。
フィゲロアの瞳が揺れはじめる。
その期を逃さず、トゥパク・アマルが続ける。
「わたしは、インカの地に生きる者たちが、このアンデスの大地の声を聴きながら、自らこの地を治め、自らの手で自らの幸福を築き上げていく世にしたい」
トゥパク・アマルは机上の蝋燭の炎に、一瞬、その研ぎ澄まされた視線を移すと、また鋭くフィゲロアを見た。
そして、すっと目を細め、低く、沈着な声で、しかし、その背後に燃えるような情熱を秘めて言う。
「フィゲロア殿、今こそ、共に、この国を我々自身の手に取り戻そうではないか!」
フィゲロアは、瞬間、己の体を電撃が貫いて走るような錯覚を覚え、ビクリと身を震わす。
彼は、全身に鳥肌が立つのを、ハッキリと感じた。
思わず、ゴクリと生唾を呑む。
ほどなく、トゥパク・アマルは再び表情を和らげると、少し遠い眼差しになって、夜の闇に彩られた窓の方に顔を向けた。
彼の端正な横顔を、蝋燭の光が濡れたように照らし出す。
室内は、水を打ったように静まり返った。
蝋燭の芯が焦げる音が微かに聞こえる。
窓を見やるトゥパク・アマルのその横顔に、フィゲロアの、あのひどく純粋な瞳が、真実を見極めようと喰い入るように注がれる。
トゥパク・アマルはフィゲロアの視線を感じながら、しかし、そのまま、納得するまで自由に見ていよ、とばかりに、じっとその体勢を保ち続けた。
暫し時が流れ、それから、トゥパク・アマルはゆっくりと首をこちらに動かした。
そして、フィゲロアの方に静かな微笑みを送る。
「そなたは、わたしが、あの『インカ皇帝』の座につくことを案じていたのか?」
「それもある」と、フィゲロアは偽らぬ声で応える。
「だが、それだけではない」
フィゲロアの声が低く響いた。
トゥパク・アマルは指を組み直し、相手の言葉を待つように、じっと耳を傾ける。
眼前の褐色の敵将が、噛み締めるように語り出す。
「確かに、この国は、植民地になった。
だが、トゥパク・アマル…植民地政策は、おまえの言うほどに絶対悪なのか?
支配する者たちは、我々支配される者に、悪事の限りを尽くしているか?
スペイン人によって、もたらされたキリスト教は、完全なる悪か?!
西洋的な文化は…?!
数知れぬ進歩的な知識は、どうなのだ?!
トゥパク・アマル…おまえだって、その恩恵を受けて生きてきたのではないのか?!」
そう言って、フィゲロアは両目を激しく吊り上げ、凄むような形相でトゥパク・アマルを睨みつけた。
「支配する事が『悪』で、支配される事は『恥ずべきこと』だとは、必ずしも思わぬ!!」
憤然と言い放ったそのフィゲロアの言葉を最後に、今、再びの沈黙が訪れる。
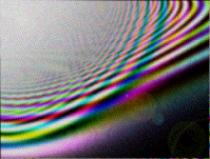
蝋燭の炎を見やりながら、今度はトゥパク・アマルが言う。
「フィゲロア殿。
世界中の植民地支配が全て『悪』とは言いきれまいという、そなたの考えは、必ずしも否定はせぬ。
広く世界を見渡せば、貧しい国家や地域を植民地として自国の一部とみなし、熱心に投資し、環境を整え、発展を助けている場合も稀にはあるかもしれぬ。
だが…」
トゥパク・アマルは蝋燭の方から、再び、眼前の敵将に体ごと向き直る。
「この国が受けている支配は、そのようなものではない。
そなたの目ならば、見ようとすれば見えるはずだ。
この国で起こってきたことが。
侵略者によって、悉く略奪され尽くし、人権を奪われ、物のごとくに扱われ、それが熾烈を極めながら今もなお続いていることを」
フィゲロアの顔を真正面に見据えて、トゥパク・アマルが言う。
しかし、フィゲロアも、また、そのトゥパク・アマルの顔を皮相な冷笑を浮かべて見返してくる。
「侵略…、侵略者?
ふ…そんな言葉は、弱い民族が自己正当化のために使う言葉なのだ!!」
トゥパク・アマルの目が、微かに、見開かれた。
その瞳の色には、僅かながら苦渋の色が浮かぶ。
それを見逃さず、追い討ちをかけるがごとくにフィゲロアが続ける。
「『侵略者』に隷属した原因は弱い民族にある。
そう…おまえの祖先のインカ皇帝たちが築き上げた国家は、民族は、弱かったのだ!!
だから、インカ帝国は侵略された。
その真実を真っ直ぐに見つめるべきは、おまえの方ではないのか?!
トゥパク・アマル!!」
フィゲロアの勝ち誇ったような表情に、さすがのトゥパク・アマルの瞳も、今、微かに怯む。
トゥパク・アマルは、「うむ…」と低く唸り、机上に視線を落とした。
「フィゲロア殿…確かに、そなたの言うことは、一理ある」
「認めるのか?」と、フィゲロアが身を乗り出した。
「西洋に比べて技術的に劣っていた部分があったことは認めよう。
だが…」
今度は、トゥパク・アマルが、しかとフィゲロアの目を見据えた。
「それはあくまで物理的なこと。
真に我々の、インカの地の民の精神が、魂が、弱かったわけでも、劣っていたわけでもない。
そのことを、混同してはならぬ。
フィゲロア殿」
トゥパク・アマルは、決然とした声で言う。
今、その彼の全身から立ち昇る青白い覇光は、いよいよその光をいや増していく。
「そして今も、インカの地の民の、その身に深く宿る魂は、決して、いかなる民族にも劣るものではない。
我々の中には、まだそれが生きている。
いかなる者とて、それを押し潰し、息絶えさせてよいはずはない。
植民地体制や西洋文化に対する肯否も議論の余地はあろうが、それ以上に、今は、現状のスペイン人たちによる治世では、目の前の民が、今この瞬間にも疲弊し死に果てつつあるという、その現実こそが重要なのだ。
このまま植民地体制下の暴政が続くならば、民の命が果てるだけでなく、遠からず、民の魂までもが死に絶えるであろう。
そなたほどの者が、このままインカの民が死に絶え、あるいは、生きた屍となるのを見過ごせるか?
手遅れになる前に、ことを進めねば何も変らぬ。
今なら、まだ間に合おう。
だが、これ以上は、据え置けぬ。
時は今なのだ!
今こそ、本来の我々自身を取り戻す時なのだ…――!!
そのためには、この国全体の政治も、法も、そのありようの全てを仕切り直さねばならぬ。
もちろん、わたしとて、多大な犠牲を伴う反乱行為なぞ、望んではいなかった。
これほどまでの多くの犠牲者を出してしまったことを、悔やまぬ日などない。
だが、他に道がなければ、その道を進むしかあるまい」

トゥパク・アマルの形相は、今、修羅のごとくに険しく、その全身が、そして、その瞳の放つ光が、青白い色から黄金色へと変わっていく。
それは、まるで太陽神の化身のごとくの迫力であった。
もはや、フィゲロアには、己の目の中に映る眼前の人物が、まぎれもなく、『インカ皇帝』そのものに見えてしまう。
錯覚だと分かっていても、もはや、その見え方を振り払うことができない。
皇帝陛下…――!!
フィゲロアの顕在意識のずっと奥深くの深層意識は、その強烈な光の前に思わず平伏(ひれふ)しそうになる。
「フィゲロア殿、我々、インカの民のために、そなたの力を貸してほしい。
我々インカ軍と共に戦おう!!」
正義に貫かれた輝くような眼差しで迫りくるトゥパク・アマルを、フィゲロアは呑みこまれるように恍惚と見上げた。
その目に、トゥパク・アマルは力強く頷き返す。
フィゲロアが、思わず、その頷きに応えそうになる。
が、彼は、いきなり、今起こったことをすべて振り払うように椅子から飛び退った。
「騙されぬ…!!」
搾り出すような声で言う。
「フィゲロア殿…」
トゥパク・アマルの声にも、苦渋が滲む。
「騙されぬ!!
口先だけなら、何とでも言えるのだ…!!」
あからさまに混乱を露(あらわ)にした顔面を歪め、フィゲロアはふらつく足取りで部屋の一隅まで行くと、いきなり置物の陰から、あの鋭利な半月刀を取り出した。
「トゥパク・アマル…、よもや、ここを生きて出られるとは思っておるまいな!!」
あれほど純粋だったフィゲロアの目が、今はひどく混濁し、ありありと狂気の色を帯びている。
さすがのトゥパク・アマルも、危険を感じた。
トゥパク・アマル自身は、フィゲロアへ半ば命を差し出すほどの覚悟と誠意の体現のために、本当に武器を持参してはいなかったのだ。
一方、敵将が握るその目前の刀は、かのクスコ戦で、彼の左腕を無情に切り裂いたのと同じものだった。
彼の左腕のまだ癒えぬ傷口が、思い出したようにズキズキと激しく痛みだす。
トゥパク・アマルは固唾を呑み、鋭くフィゲロアを観察した。
フィゲロアの目はひどくすわり、激しい混乱に混濁を深めながら、その焦点さえも危うくなっている。
今、フィゲロアの脳裏には、あのモスコーソ司祭の言葉がキンキンと響き渡っていた。
『フィゲロア殿、忠良なる神の御前の子羊よ、本当にそなただけが頼りじゃ。
この国の神聖なるキリスト教を悉く血と火で汚すあの謀反人トゥパク・アマルから、この国を、そして、このか弱き牧者を守っておくれ!!』
そして、あの植民地巡察官アレッチェの言葉が、ドロドロとした赤黒いイメージと共に、ひどい大音響で耳元にこだまする。
『トゥパク・アマルに思うようにさせてはならぬ。
あの男は、再び「インカ皇帝」として君臨し、独裁政治を敷こうとしている。
そなたがそれを防ぐのだ!!』
さらには、眼前の先刻のトゥパク・アマルの言葉が…――。
『インカの地の民としての誇り、その身に深く宿る魂は、決して、いかなる民族にも劣るものではない。
我々の中には、まだそれが生きている。
今こそ、本来の我々自身を取り戻す時なのだ。
今こそ、スペインの植民地体制から独立するのだ。
この国を我々自身の手に取り戻すのだ!!』
フィゲロアの頭の中で、3人の言葉が激しく嵐のように渦巻いた。
「うわああああ!!」
いきなり狂ったような叫び声を上げるフィゲロアを鋭く見据えるトゥパク・アマルの目の中で、その褐色の敵将の呼吸はひどく荒々しくなっている。
フィゲロアは、肩を激しく上下させながら、血走った眼(まなこ)でその危険な半月刀を握り締め、にじり寄るように、確実に迫り来る。
トゥパク・アマルは、敵を刺激せぬよう、慎重に椅子から立ち上がった。
そして、すぐに次の動作に移れるように、僧衣の裾を素早く整える。
彼は、相手を深い混乱に貶めてしまったことを申し訳無くさえ思うと共に、事態がまずい方向になった、と感じる。
常軌を逸した相手との話し合いは、これ以上は無理だった。
もはや、話し合いはこれまでか…――!
まだ話がついていないだけに、トゥパク・アマルの中に苦々しい思いが渦を巻く。
しかしながら、この事態に至っては、ともかくも、この場を安全に逃れることが最優先であった。
ぬめるような不気味な光を放つ巨大な三日月型の刃を構えながら、ジリジリと間合いを詰めてくるフィゲロアを、彼は鋭く見据えた。
さすがに武勇に秀でた敵将だけあって、この状況下にあっても、刃を構えるその姿勢に隙が無い。
一方、まだ術後の傷の癒えぬトゥパク・アマルの左腕は、今は完全に通常の機能を失っている。
トゥパク・アマルの横顔に、ついに一筋の汗が流れた。
よもや、ここまでか…!!――彼の中に、そんな念が突き上げる。
武器を持参していないトゥパク・アマルは、しかし、それでも、右手で敵の襲撃に構えの姿勢を取った。
その動作に触発されたがごとく、今や常軌を逸した眼のフィゲロアが、全く戦場と違わぬ勢いで、半月刀をトゥパク・アマル目掛けて激しく振り下ろす。
「トゥパク・アマル、覚悟!!」
ビョウッと、不気味な音が空(くう)に響く…――!!

だが、確実に仕留めたと思ったはずのフィゲロアには、手応えが伝わってこない。
「!!?」
一方、完全に間一髪のところで俊敏に身を翻して刀をかわしたトゥパク・アマルが、次の瞬間には、その僧衣の裾が裂けるほどの凄まじい勢いで己の足を蹴り上げた。
そして、そのままフィゲロアの足を激しく薙(な)ぎ払う。
鉄棍のように固く鍛えられたトゥパク・アマルの足払いを受け、同じく鍛えられているはずのフィゲロアの足は、しかし、強烈な衝撃に大きく傾いた。
この時にはすっかり冷静さを失っていたフィゲロアは、そのまま大きくバランスを崩し、前方へ前のめりになった。
その一瞬に、トゥパク・アマルはフィゲロアの背後に照準を合わせ、頭頂の急所に右肘(ひじ)を鋭く打ち落とす。
たちまち褐色の敵将は気絶して床に崩れた。
彼の手から、半月刀が鋭い金属音を立てて床に転がり落ちる。
「フィゲロア殿、すまぬ…」
そう言い残すと、トゥパク・アマルは素早く頭からベール代わりの布を被り直し、何事もなかったかのようにその部屋を出ると、門前で見張る衛兵たちに軽く会釈をしてそこを通り過ぎた。
そして、素早い身のこなしでフィゲロアの屋敷から遠ざかると、ロレンソの待つクスコの夜の繁華街の方にその姿を消し去った。


